
| 目次 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 本稿では、和暦の年月日・数えの年齢に和数字を使い、西暦の年月日には算用数字を使っている。(ただし、図の中の月日は、和暦月日も算用数字にしていることがある。) |
また云はく、「花山院、御即位の日に、大極殿の高座[たかくら]の上において、いまだ剋限をふれざる先に、馬内侍を犯さしめ給ふ間、惟成の弁は玉佩ならびに御冠[おんかうぶり]の鈴の声に驚き、「鈴の奏」と称[い]ひて、叙位の申文[もうしぶみ]を持参す。天皇御手をもって帰さしめ給ふ間、意に任せて叙位を行へり」と云々。(新日本古典文学大系32『江談抄 中外抄 富家語』岩波1997)(p6)惟成の弁が花山天皇の近臣であることをいいことに、勝手に叙位を進めたという政治的揶揄を込めているとも解されるが、よくわからない。
花山院は、即位の日に、大極殿の高座の上で、まだ式典の進行の合図が鳴る前に、馬の内侍を犯していた。惟成の弁は玉佩や御冠の鈴の音がしているのに驚いて、式典後半に必要となる叙位の申し文を持って玉座に近づいた。天皇は手で惟成を追い払ったので、惟成はそのあとは勝手に叙位を行った。
花山院御即位の日、馬内侍、けん帳[「けん」は寒の2つの点が衣]の命婦と為りて進み参る間、天皇高御座[たかみくら]の内に引き入れしめ給ひて、忽ち以て配偶す、と云々。(新日本古典文学大系41『古事談 続古事談』岩波2005)(p34)即位式は天皇一世一代の重大な行事であり、高御座は宗教的な権威づけのために荘重な造りになっている(その形状は鳳輦と類似している)。高御座には帳が下がっていて、天皇はその内側に女官を引きこんで犯した、ということだろう。花山天皇の即位は永観二(984)年八月のことで、古代天皇制が変質し中世王権が成立しようとしている過渡期であった。そうであっても、即位式が重大な儀式であることは当然であり、後宮など私的な空間でのスキャンダルとはまったく質が異なる。おおっぴらになってしまうのは当然である。
花山院は即位の日に、高御座の帳をかかげる役の馬内侍が進み出てきたので、高御座の内に引き入れてたちまち交わった。

前引『古事談』の脚注は馬内侍に関して詳しく述べていて、馬内侍は二人いたこと、もちろん「けん帳の命婦」ではありえないこと、だが当日の花山院の奇行に関する何らかの伝承が存在していてそれが有名人である「馬内侍」に結びつけられていった可能性を推論している。その部分を引用する。月を見てゐなかなるをとこをおもひ出でてつかはしける
こよひ君いかなるさとの月をみて都にわれをおもひいづらむ
(新帝は早めに着座しており、けん帳命婦に先立ち登場する女官があって、このときは)剣璽内侍として従っているのが紀順子と源平子。源時中の妻に平子命婦がいるが、関係不明。馬内侍と呼ばれる人は二人いて、その一人は文徳源氏だが、右馬権頭時明を父か叔父(養父)とするのであれば、掌侍源平子とは別人。ただ、何らかの伝承が比較的有名な馬内侍に仮託された(あるいは成長した)可能性はある。(前掲書p29)花山天皇は17歳で即位している。これは決して若すぎる即位とは言えない。例えば5代前から即位の時の年齢をあげてみると(並記したのは在位年数)、
醍醐(13,33)-朱雀(8,17)-村上(21,21)-冷泉(18,2)-円融(11,15)-花山(17,2)
すなわち、花山の即位の年齢は、当時としては普通のことであり、むしろ異様なのは、冷泉とともに在位が2年間と、非常に短かったことである。冷泉は花山の父であり、精神に問題があったとされている(次節で扱う)。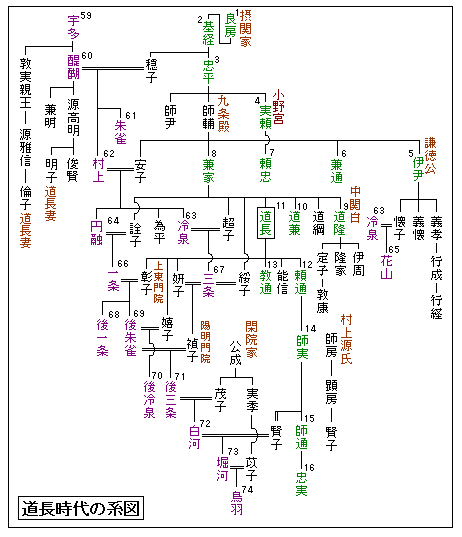
冷泉院の御即位は、大内紫宸殿において行はる、と云々。神妙の儀なり。主上頗る例ざまにも御坐[おはしま]さず、大極殿において此の事を行はれなば定めて見苦しきか。小野宮殿の高名、此の事なり、と云々。(前掲書p35)小野宮・藤原実頼というのは、忠平の長男で母は宇多天皇の女[むすめ]・順子。村上天皇の時代には弟・師輔とともに左・右大臣となり、「天暦の治」と賞讃された。村上天皇に実頼・師輔はそれぞれ女を入内させたが、実頼女は皇子を生まず、師輔女・安子は後の冷泉・円融の2男子を生んだ。そのことが兄弟の家系の大きな差となる。
冷泉院の即位は、大内の紫宸殿で行われた。結構なことであった。主上はひどく普通ではないので、大極殿で即位式を行えばきっと見苦しいことになったであろう。小野宮(藤原実頼)がうまくおやりになったのは、まさにこの事である。
なお、本稿では〈王権〉という語を使用するが、それは「国家権力」ないし「国家」というと、われわれがつい「国民国家」を想像してしまいがちなので、それを避けたいためである。平安時代において、天皇即位式が大極殿で行われなかったのは、わずか3回しかない。その初例が上の冷泉天皇の場合である。残り2つの例外は、いずれも大極殿が焼失している時期である。後三条天皇の場合は治暦四年(1068)七月であったが、その約10年前に「新造の内裏焼け、大極殿・朝集堂も焼ける」という火災があり、それの復旧ができていなかった。それで、即位式は太政官庁で行われた。安徳天皇の場合は、治承四年(1180)四月であったが、『方丈記』で有名な「安元の大火」(1177)で大極殿が焼失しており、紫宸殿で行われた。
〈王権〉に包摂されている人々(王-官僚-人々)とその専有している土地をあわせて、「国家共同体」としてもよいわけだが、「国家共同体」に包摂されていない人々もいくらでも存在していたことを忘れがちである。
経済関係で結ばれていても、〈王権〉に包摂されていない人々もありえたであろう。異なる〈王権〉同士の人的・物的交流(敵対も含めて)がありえたであろうが、そういう交流の外に自存していた人々もあったであろう。
同じく(治承四年)四月二十二日、新帝(安徳)御即位あり。大極殿にてあるべかりしかども、ひととせ炎上(安元の大火)ののちは、いまだ造り出されず。「太政官の庁にておこなはるべし」とさだめられたりけるを、そのときの九条殿(兼実)申させ給ひけるは、「太政官の庁は、およそ人の家にとらば、公文所体の所なり。大極殿なからんには、紫宸殿にて御即位あるべし」と申させ給ひければ、紫宸殿にて御即位あり。冷泉天皇は「御邪気」のために、大極殿へ行って即位式をあげることが不可能だった。そういう不吉な天皇の例に合わせるのではなく、「延久の佳例」(治暦四年の翌年に改元して延久となった)に合わせたら良かったのにと噂した、というのである。
「去んぬる康保四年十一月一日、冷泉院の御即位、紫宸殿にておこなわれ候ふことは、主上御邪気[おんじゃけ]によって、大極殿へ行幸かなはざりしゆゑなり。その例いかがあるべからん(その例と一致するのはいかがなものか)。ただ延久の佳例[後三条の場合]にまかせて、太政官の庁にておこなはるべきものを」と人々申しあはれけれども、九条殿の御はからひのうへは力およばず。(『平家物語 上』新潮日本古典集成p303)
「故小野宮右大臣[実資]語りて云はく、「冷泉院、御在位の時、大入道殿[兼家]たちまち参内の意有り。よりてにはかに単騎馳せ参り、御在所を女房に尋ぬ。女房云はく、『夜の御殿[おとど]に御[おは]します。ただ今、御璽の結緒を解き開かしめ給ふなり』といへり。驚きながら門[かど]を排[おしひら]きて参入す。女房の言[ことば]のごとく筥[はこ]の緒を解き給ふ間[ころほひ]なり。よりて奪ひ取り、本[もと]のごとくに結ぶ」」と云々。(前掲書、第二の三p34)「故小野宮右大臣」は藤原実資(さねすけ 957~1046)のこと。実資は実頼の孫だが長じて実頼の養子となって小野宮流を継ぐ。『小右記』の作者として名高い。『江談抄』は大江匡房の談話記録であるが、この冷泉院の不行跡は、匡房が実資から聞いた話だとして紹介しているのである。
冷泉天皇のとき、兼家が突然の急用で、夜中に独り馬で宮中に駆けつけたことがあった。居合わせた女房に天皇の居場所を尋ねたところ、「夜の御殿で御璽の緒を解こうとしておられます」と急を告げた。兼家はいそいでかけつけて、天皇から筥を奪い取って、もとの如く結んで安置した。「夜の御殿」は天皇の寝所で、内裏の清涼殿の中にある。宝剣・御璽も同室に置かれ、天皇はかならずそこでそれらを守りつつ就寝した。なお、三種の神器のもうひとつの鏡は温明殿[うんめいでん]の内侍所(賢所ともいう)に安置してあった。
神璽宝剣、神の代よりつたはりて、帝の御まもりにて、さらに開け抜く事なし。冷泉院、うつし心なくおはしませばにや、しるしのはこのからげ緒を解きてあけんとし給ひければ、箱より白雲たちのぼりけり。をそれて捨て給ひたりければ、紀氏の内侍、もとのごとくからげられけり。宝剣をぬかむとし給ひければ、夜御殿、ひらひらとひかりければ、おぢてぬき給はざりけり。かかるめでたきおほやけの御たから物、目の前に[壇ノ浦で]うせにき。(『古事談 続古事談』1の2 p604)これら宝物は、厳重に保管してあるというだけではなく、その封印の仕方、箱や紐の作り方、紐の結び方などのそれぞれに重要な意味づけと方式があったはずである。そういう事に通じている内侍がいて、管理していたのである。
本三位[ほんざんみ]の中将[重衡]の北の方大納言の典侍、内侍所の御櫃を取りて海へ入れんとし給ふが、袴のすそを船に射つけられて蹴つまづき給ふところを、兵[つはもの]取りとどめたてまつり、御唐櫃の錠をねぢ切って、御蓋をあけんとしければ、たちまちに目くれ、鼻血垂る。平大納言時忠の卿生捕られておはしけるが、これを見て、「あな、あさましや。あれは内侍所と申す、神にてわたらせ給ふものを。凡夫は見たてまつらぬことを」とのたまへば、九郎判官[義経]、「さることあらんずるぞ。そこのけよ」とて、平大納言に申して、もとのごとく納めたてまつる。(同前下巻「早鞆」p250)ここまでの情報だけだと、冷泉院について誤解してしまうであろう。
冷泉院へ筍[たかんな]奉らせ給ふとてよませ給ひける 花山院御製ごく素朴に詠んだタケノコ贈答の和歌で、天皇親子じゃないとこんな素直さは詠めないのじゃないか、と思うぐらいだ。技巧やてらいを忘れた次元で詠まれている感じのよい和歌だと思う。この和歌贈答は『大鏡』にも引かれている(第三巻「伊尹(花山天皇)」古典体系本p151)が、『大鏡』のその辺りは後に扱う。
世の中に経[へ]るかひもなき竹の子はわが経む年をたてまつるなり
御かへし 冷泉院御製
年へぬる竹の齢をかへしてもこのよをながくなさんとぞ思ふ
年を重ねるかいもない子として、父上が長生きしてくださるように自分の歳を差し上げます。「竹の子」に自分をたとえた。
歳とった自分の年齢をお前に返してやって、お前の寿命を長くしたいものだと思う。「このよ」は「子の代」。
五日甲戌。南院焼亡。去三月十四日冷泉院自三条宮所遷御也。此火及但馬守源則忠宅同年の三月十四日条を参照すると、「冷泉上皇が三条宮から南院へ遷御なさった」という記事しかなく、冷泉院の住居の変更の情報確認ができるが、新しい内容はない。いずれにせよ、半年余り前に「南院」に三条宮から移ってきていたが、その南院が火事となったのである。しかも、その火事は「南院焼亡」だけではなく、「但馬守源則忠」の邸宅をも延焼したわけであるから、ボヤ程度ではない重大な火災であったと考えられる。『日本紀略』が書き残したのであるから、ある程度の重大性があった火災であった、のであろう。
五日きのえね・いぬ。南院が焼亡した。去る三月十四日に冷泉院が三条宮から遷御なさっていた御在所であった。この火は但馬守・源則忠の邸宅に及んだ。
源則忠(949~?):盛明親王の子、母は菅原在躬女。近江介、越前守、民部大輔、中宮権亮等を経て、従三位左京権大夫に至った。長保二年(1000)七月、中宮彰子は、彼の堀河第に移御したことがある(『権記』『記略』)。漢詩に巧みで尚歯会に関係した。寛弘五年(1008)飯室にて出家後の動向は未詳。(執筆:角田文衛『平安時代史事典』 )つまり、源則忠の邸宅というのは「堀河第」のことである。角田文衛が示している「中宮彰子の移御」は、『日本紀略』長保二年(1000)七月廿三日条である。
自左大臣土御門第移御権亮源則忠朝臣堀河宅公卿并侍従。諸司諸衛供奉如常。この中宮彰子(道長の娘であるから、土御門第に同居していた)が堀河第へ移ったというのであるが、そのとき「供奉常の如し」とあることによって、則忠邸=堀河第がかなりの大邸宅であることがわかる。土御門第に引けを取らないほどの規模であろう。
中宮は左大臣道長の土御門第より、権亮源則忠朝臣の堀河宅へお移りなさった。公卿や侍従また諸司諸衛の供奉はいつもと変わりがない。
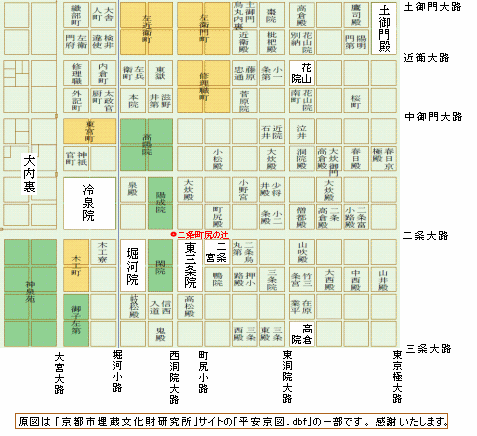
上図に書き込んだ「二条町尻の辻」は、岩波古典体系本『大鏡』の補注の図による(p463)。さて、次にこの火事について『御堂関白記』の記載を見よう。この筆者道長はこの時期、天皇を除けば最高権力者であることはまちがいなく、その天皇(一条)も彼の妹・詮子の子つまり甥であり、彼の娘・彰子を中宮としている。そういう立場の人物の日記が残っていること自体、驚くべきことだ。
五日、甲戌、渡東三条見作事、次入道(義懐)中納言被来、入夜帰、亥時許未申方火見、冷泉院御在所南院、馳参、東三条御西門、即東対御装束御座、夜深還出、崋山院参給、諸卿皆以参入、道長の居宅・土御門第は上図の右上に位置する2町を占める鴨川沿いの邸宅である。道長は土御門第から東三条邸で行っている造作の様子を見に行った。そのところに義懐入道がやって来た。義懐は伯父・伊尹[これまさ]の息子、すなわち道長の従兄である。(義懐は道長より11歳年長。義懐の出家は花山天皇の突然の出家(986)で、兼家との政治闘争に敗北したため。伊尹も兼家もとうに死没している。道長はこの年(1006)40歳。しかし、義懐と道長の関係はうまくいっていたようである。義懐入道はときどき道長を訪問している。
五日きのえいぬ。東三条邸の造作を見に出かけた。次に義懐[よしちか]・入道中納言がおみえになった。夜に入って帰った。亥の剋(午後11時)ごろに、未申方(南西)に火が見えた。冷泉院がおられる南院に駆けつけた。冷泉院は東三条邸の西門におられた。ただちに東対に御座の準備をして御在所とした。私は夜深くなって出て、帰った。花山院がいらっしゃった。諸卿も皆参っていた。
五日、甲戌。 東三条第造営/東三条第南院焼亡この倉本一宏『全現代語訳』で、“おや?”と思うのは、火元となった「南院」が「東三条第南院」と特定されていることである。広大な屋敷の敷地の南側に独立した第を建てて、それを「南院」と呼ぶようである。したがって、単に「南院」とあっても、それがどの邸第の南院であるのか、よく調べないと分からないのである。
東三条第に赴いて造営を検分した。次に入道中納言(藤原義懐 よしちか)が来られた。夜に入って、土御門第に帰った。亥剋の頃、南西の方角に火事が見えた。冷泉院御在所の東三条第南院である。馳せ入った。冷泉院は、東三条第の西門にいらっしゃった。すぐに東対に御座の御室礼(しつらい)を行った。夜遅く、土御門第に帰った。花山院が参られた。諸卿も皆、参入した。(前掲書 上巻p264)
中にも、冷泉院の南の院におはしましし時、焼亡[せうまう]ありし夜([以下略])この「南の院」に頭注がついているのだが、次はその頭注全文である。
中でも、冷泉院がちょうど南の院にいらっしゃった時、そこが火事で焼亡してしまった夜のことですが、
冷泉院構内の南の方にあったらしく、冷泉院が三条の宮からここにお遷りになり、後にその御子孫の敦道親王の御所となった。(前掲書 p267)邸宅としての「冷泉院」は、上図にもあるが、4町という巨大な敷地をもち、大内裏の東南の至近地という好条件の場所を占めている。嵯峨天皇が離宮として造営し、そのあと後宮[天皇が退位後、上皇として住まう邸宅]として使われた。はじめは「冷然院」と言われたが、火災が続いたので天暦八年(954)「冷泉院」と改名した。したがって、冷泉上皇の名前とは直接関係はない。後宮であるので、冷泉上皇が冷泉院を使っていてもすこしも不自然ではないのである。たとえば、『平安時代史事典』の「冷泉院」の項目では
天禄元年(970)三度目の火災にあい、当時当院を用いた冷泉上皇は朱雀院に移っている。(執筆 関口力)と書いている。
なかにも、冷泉院の、南の院におはしまししとき、焼亡ありし夜、[花山院が]御とぶらい[お見舞い]にまいらせ給ひし有様こそ、不思議にさぶらひしか。御親の院[冷泉]は、御車にて二条町尻の辻に立たせ給へり。この院[花山]は、御馬にて、頂きに鏡入れたる笠、頭光にたてまつりて[阿弥陀かぶりになさって]、冷泉院は南院から避難して東三条邸の西門に至る途中、二条町尻の辻に車が止まった。そこに、馬で駆けつけた花山院が、鏡を付けた笠をあみだにかぶった異装で、ひざまずいて父・冷泉院に挨拶した。ちょうどそこで、車の中から冷泉院が高らかに神楽歌を唄いだした。御神楽の儀は庭にかがり火を焚いて行うから、高梨明順が火事の火と掛けて、不謹慎にも「神楽の庭火がさかんですな」と言ったので、皆がたまらず笑い出してしまった。
「いづくにかおはします いづくにかおはします」
と、御てづから[自ら]人ごとに尋ね申させ給へば、
「そこ、そこになん」
と聞かせ給ひて、[冷泉の]おはしまし所へ近く[馬から]おりさせ給ひぬ。
御馬の鞭、かいな[腕]に入れて、御車の前に、御袖うち合はせて、いみじうつきづきしうゐさせ給へりしは[随身などがするように似つかわしくひざまづいておられたのは]、さる事やは侍りしとよ[そんな事って、いったい、あったもんでしょうか]。
それに又、冷泉院の、御車のうちより、高やかに神楽歌を唄はせ給ひしは、さまざま興あることをも見聞くかなと、おぼえ候し。明順[あきのぶ]のぬしの、
「庭火のいと猛[もう]なりや」[神楽の庭火が燃えさかっておりますなあ]
とのたまへりけるにこそ、万人え堪へず、笑ひ給ひにけれ。(『大鏡』岩波古典体系21 「第三巻伊尹(花山天皇)」p149)(引用は、読みやすくなるように適宜漢字を宛てた。以下の引用でも同様)
花山院の御時のまつりごとは、ただこの殿[義懐]と惟成[これしげ]の弁として行ひ給ひければ、いといみじかりしぞかし。その帝[みかど 花山]をば「内劣りの外めでた」とぞ、世の人申しし。「花山院の御時のまつりごと」というのは、わずか在位2年間であった花山天皇の“治世”のことをさしている。そのときのエビソードとして、義懐が花山院の暴走をなんとかくい止めた一例が語られる。まず【第1段落】。
花山天皇の時の政治は、義懐や惟成らの賢臣が手腕を振るったので、たいそう立派だった。それで、その天皇を「私生活はひどいものだったが、表向きは好評だった」と、世の人は評判した。
「冬臨時祭の、日の暮るる、悪しきことなり。[賀茂の臨時祭が日暮までかかるのは、よくない]辰の時[午前8時ごろ]に人々まいれ」賀茂の臨時祭を明るいうちに終わらせようといって、花山天皇が集合は午前8時だぞ、と命じた。そんなに早く始まるわけがないと皆思って、舞人たちが衣裳を貰いに行ってみたら、はやくも、花山天皇は衣裳を着けて待っていた、というのである。
と(花山天皇が)宣旨下させ給ふを、
「さぞおほせらるるとも、巳午時[9時~正午]にぞ始まらん」
など思ひ給へりけるに、舞人の君達、装束たまはりに参りにけければ[支給される衣裳を貰いに行ってみたら]、帝は御装束たてまつりて[すでに、花山天皇は衣裳を身につけて]立たせおはしましけるに、この入道殿[道長]も舞人にておはしましければ、このごろ語らせ給うなるを、伝へて承るなり。[道長様も若くて舞人のひとりだったので、この頃になって思い出話にお話になるのを伝え聞いて、世継が承ったのです](世継は、『大鏡』の語り手)
あかく大路など渡るがよかるべきにやと思ふに[明るいうちに祭の行列が大路を渡り終わるのがよいというご配慮だろうとみなが思ったが]、帝、馬をいみじう興じさせ給ひければ、[舞人の馬を]後涼殿[こうろうでん]の北の馬道[めどう]より通させ給ひて、朝餉の壺[あさがれひのつぼ]に[舞人を]引き下ろさせ給ひて、殿上人どもを乗せてご覧ずるをだに、あさましう人々思ふに[言いようもないヒドイことと人々が思ったのに]、はては、[天皇自ら]乗らんとさへせさせ給ふに、すべきかたもなくてさぶらひあひ給へるほどに[一同はどうしようもなくただ居るだけであったときに]、さるべきにや侍りけん[そういう回り合わせだったのでしょう]、入道中納言[義懐]差し出で給へりけるに[お出ましになったので]、帝、御おもていと赤くならせ給ひて、術[ずち]なげにおぼしめしたり。舞人たちが衣裳を着けたりしている場所へ祭りの行列に参加する馬が連れてこられると、花山天皇は馬がとても好きだったので、後涼殿の馬道[回廊の一部を切り離して板が渡してあり、馬が通るときは板を外ずして通せる]から内裏の奥深くへ馬を導き、清涼殿の朝餉の壺という所まで入り、そこで舞人を馬から降ろし、殿上人を乗らせた。そのうち天皇自身が馬に乗りたくなってきて、乗ろうとした。そこへ義懐がやって来たので、いたずらが見付かった子供のように、花山はすっかり顔を赤くして、困っていた。
中納言[義懐]もいとあさましう見奉り給へど、人々の見るに制し申さむも、なかなかに見苦しければ、もてはやし興うじ給ふやうにもてなしつつ[その場をもりあげ、面白がっているように装って]、自ら、下襲[したがさね]の尻挾みて、乗り給ひぬ。さばかり狭き壺に折り廻し、面白く上げ[終了する]給へば、御気色なおりて、義懐は、皆の前で花山天皇を制止するのはマズイと考えて、自分から馬に乗って興じてみせ、その場を納めた。その義懐の本心を周囲の誰もが分かっていたからこそ、こうして言い伝えられているのだ(と世継が述べる)。それでも、中には義懐が実際に乗馬までするのは行き過ぎじゃないか、と批判する人もいた。
「悪しきことにはなかりけり」
とおぼしめして、いみじう興ざせ給ひけるを、中納言あさましうも哀れにもおぼさるる御気色は、同じ御心に良からぬことをはやし申し給ふとは見えず[天皇と同じ心で、義懐がよくないことをおだてはやしているとは見えず]、誰もさぞかしとは見知り聞こえさする人もありければこそ、かくも申し伝へたれな。[誰も義懐の本心はこうだったろうと思い、申し上げる人もあったからこそ、このように申し伝えているのでしょう]また、「[義懐が]みづから乗り給ふまでは、あまりなり」と言ふ人もありけり。
これならず、ひたぶるに色にはいたくも見えず、ただ御本性のけしからぬさまに見へさせたまへば、いと大事にぞ。民部卿・源俊賢は前掲道長時代の系図に書き込んでおいたので、確認して欲しい。貴族源氏で、後醍醐天皇の孫である。父・高明の失脚(安和の変 969)によって出世が遅れたとされるが、藤原公任、斉信、行成らとともに一条朝の四納言といわれる能吏。あるいは賢臣。
[この例だけでなく、花山の乱心は、むやみに表面に現れるのではなく生まれつきの本性が壊れているようにお見えなさいますので、深刻なんです]
されば源民部卿[俊賢 としかた]は、
「冷泉院の狂ひよりは、花山院の狂ひは術なきものなれ」
と申し給ひたれば、入道殿[道長]は、
「いと不便なること[不都合なこと]をも申さるるかな」
とおほせられながら、いといみじう笑はせ給ひけり。 (前掲書p146~147)
| 寛弘三年(1006) | 十月五日 | 冷泉院の火事 |
| 同 | 十一日 | 冷泉院の御座所の造営、源成方朝臣の宅を借りて、築地の造営など。 |
| 同 | 十三日 | 御座所の造営を見分。 |
| 同 | 二十一日 | 成方宅の新御座所に遷御。朝廷から冷泉院に頂き物あり。 |
| 同 | 十二月二十六日 | 法性寺供養に冷泉院からも右兵衛督憲定が使わされた。 |
| 寛弘四年(1007) | 正月三日 | 冷泉院のところで拝礼。しかるべき人々の昇殿あった。 |
| 同 | 八月十日 | 金峰山詣でのとき、三十八ヶ所の神々へ理趣経などの献げ物のなかに、一条天皇・冷泉院・中宮彰子・東宮居貞(三条)の順で出ている。冷泉が重視されているが、花山は登場しない。 |
| 同 | 十月二日 | 冷泉院第4子の敦道親王薨去(於東三条第の南院)。 |
| 寛弘五年(1008) | 正月四日 | 冷泉院に参る。 |
| 同 | 正月七日 | 冷泉院の御年給を藤原忠経に賜ることの承認。 |
| 同 | 正月十一日 | 冷泉院の昨年の御年給によって、右兵衛佐藤原道雅を正五位下に加階した。 |
| 同 | 三月九日 | 花山院崩御。しかし、冷泉院への言及なし |
| 寛弘六年(1009) | 九月四日 | 冷泉院が痢病で、その見舞いに行く(東三条第南院) |
| 同 | 七日 | 冷泉院に参る。 |
| 寛弘七年(1010) | 二月二十六日 | 冷泉院宣旨同之。東宮(居貞)の妍子との婚儀のお祝品のことか。 |
| 寛弘八年(1011) | 正月三日 | 冷泉院に参る。 |
| 寛弘八年(1011) | 八月三日 | 冷泉院、御悩有り。参る。(東三条第南院が御在所) |
| 同 | 五日 | 冷泉院に参る。 |
| 同 | 十月十九日 | 冷泉院参る。御悩甚だ重し。 |
| 同 | 二十四日 | 早朝冷泉院に参る。御悩重いといえども、未剋に退出。これはこの何日か自分に病悩あり、長く候うことができないから退出するのである。夜に入り橘則忠が来て、院の御悩極めて重く、不覚であるという。よって、馳せ参ず。その時冷泉院崩御。しかるべき処置を指示して、深夜に帰った。 |
| 同 | 二十五日 | 早朝に参内し、天皇に冷泉院崩御を報告。すぐ(故)冷泉院のところへ参った。主計頭[かずえのかみ]安倍吉平[よしひら]を召して、雑事を問う。勘申して云うには、「御入棺は経の亥の刻[深夜11時]、御棺の造り初めは申の刻[夕の4時]、御葬送の日は来月の十六日がよろしいでしょう」。天下に大赦を行った。 |
| 同 | 二十六日 | (故)冷泉院へ参った。 |
| 同 | 二十七日 | (故)冷泉院へ参った。 |
| 同 | 二十八日 | (故)冷泉院のところで、五七日の御法事を院司らと定めた。 |
| 同 | 三十日 | 故院に参る。 |
| 同 | 十一月四日 | 故院に参る。西洞院大路の東西を焼く火災あり。 |
| 同 | 五日 | 故院に参る。内裏で、三条天皇は故院の(七七日の)御斎会を皇后宮大夫(公任)が奉仕するようにおっしゃった。 |
| 同 | 七日 | 皇后宮大夫らが御斎会の準備を始めた。故院の五七日の御法事は院司たちが奉仕すべきだ。 |
| 同 | 八日 | 初雪降る。雪を踏んで故院に参る。(12月11日) |
| 同 | 十三日 | 故冷泉院に参入。(藤原)惟貞と(安倍)吉平をつかわし、故院の御葬所と御陵所を見分させた。帰ってきて報告するところによると、「桜本寺の北方に平地があり、御葬にも御陵にもよい」と。また御葬の御前の僧と五七日法事の僧の名を確定した。皇后宮大夫が七七日の御斎会の僧名や雑事を、左仗座において定めた。 |
| 同 | 十五日 | 天皇が「内裏に伺候せよ。故冷泉院の御葬送の御供には、内大臣(藤原公季)が供奉することになっている。汝は内裏に参入せよ」と言われたので、それに従うと奏聞し、退出した。 |
| 同 | 十六日 | 冷泉院の御葬送があった。故冷泉院の御在所に参入して雑事をこなった。内(三条天皇)からの召しが有ったので、参入した。「内裏に伺候せよ」ということであった。私の本意としては、故冷泉院御葬送の御供に供奉すべきであった。ところが、天皇の仰せが有ったので、御葬送には参らなかった。戌四剋に、御葬送が始まった。同じ時刻に、天皇は倚廬[いろ 服喪中の天皇の籠もる仮屋]に籠られた。下侍の間において、内侍が御釼に伺候した。その後、皆は朔平門の外に出て、素服を着した。私・春宮大夫(藤原斉信 ただのぶ)・皇后宮大夫・右宰相中将(藤原兼隆)・殿上人たちであった。女房たちも、また同じく着した。この夜、私は倚廬に伺候した。 御葬送所に奉仕したのは、(藤原)公信(きんのぶ)朝臣であった。公信朝臣が帰り参った後には、また(大江)景理(かげまさ)が奉仕した。翌朝は、また(藤原)通任(みちとう)朝臣が奉仕した。 |
| 同 | 十七日 | 御葬送に奉仕した人々は故冷泉院の御在所に帰ったということを聞いた。私も、内裏から御在所に参入した。状況を問うて、退出した。 |
| 同 | 十八日 | 内裏に参入。夜に入り罷り出ず。まず故院に参った。 |
| 同 | 二十五日 | 冷泉院の御陵に沙弥廿人。御念仏を始めた。 |
| 同 | 二十八日 | 冷泉院に参る。五七日の御諷誦は常の如し。 |
| 同 | 二十九日 | (この日が五七日法事)故院の院司たちが、五七日の御法事を本院(冷泉院)で奉仕した。早朝(故院の御在所に)参った。御装束のこと(室礼)が終わった。(このあと布施のことなど細かい記事がある)(清涼殿で御帳の帷 とばりが焼ける不審火があった) |
| 同 | 三十日 | 内裏から出て、故院(の御在所)に参る。 |
| 同 | 十二月三日 | 故院(の御在所)に参る。内大臣(公季)と僧たちが沐浴。 |
| 同 | 七日 | 早朝に冷泉院(の御在所)に参った。この日(七七日の)御斎会が行われた。夜に入って、故院の念仏会に参加した。僧十人に夜の装束を布施した。長年冷泉院に奉仕してきた志を表すためである。 |
| 同 | 八日 | 内裏から出て、故院に参る。 |
| 同 | 十一日 | 冷泉院の御念仏が結願した。大内(三条天皇)から僧たちに布施の絹を賜った。 |
| 同 | 十二日 | 冷泉院の御四十九日である。内(三条)の御諷誦は故一条院に対する諷誦と同じでこの何日間のとおりあった。 |
| 長和元年(1012) | 二月五日 | 大原野祭は本来は中宮が奉仕さるべきものであるが、中宮(妍子)が冷泉院の服喪中であるから、代わって我が家(土御門第)で饗応する。 |
| 同 | 十月六日 | 冷泉院の1周忌「周忌御斎会」 |
三条天皇を決定的に不利にしたのは、みずからの眼病であった。長和三年(1014)以降病状が悪くなったが、眼が見えなくては官奏や、叙位・除目が行えないのである。長和四年(1015)八月には、官奏を代わって見るように道長に言ったが、道長は辞退し、政務は停滞し、三条天皇は追いこまれていった。(大津透『道長と宮廷社会』p342)脚気や糖尿病などのより重大な病気をかかえていたのであろう。長和五年(1016)一月に、九歳の後一条天皇に譲位し、翌年寛仁元年(1017)に没している。
心にもあらで浮き世にながらへば 恋しかるべき夜半の月かなは、三条帝が譲位を決意したときの歌といわれている。こういう歌を天皇の名歌として残し(後拾遺和歌集)、また定家は「百人一首」にも選んだわけであり、こういうところにも、中古期の天皇観がうかがわれる。近代のゴチゴチの天皇絶対制に馴れた眼からは、“こんな厭世の歌を残していいの”と気を廻してしまいそうである。(ついでに言えば、わたしはこれを名歌だと思う。定型的なように思えるがよく味わうと、「夜半の月」を恋しいとするところに眼病を病む人のコスモロジーが現れている。)
道長は後一条天皇が即位して摂政になるまで、三条天皇の時期に一時准摂政となったことを除いて、一貫して関白にはならず、筆頭左大臣で内覧の地位を保ったのはなぜかということである。道長は関白になれなかったわけではなく、意図的にならなかったと理解すべきだろう。(大津透、前掲書p84)「内覧」は太政官が天皇に奏上する書類を、あらかじめ見る役目であるが、それは関白の重要な機能である。関白はその機能にさらに拒否権が加わるのだと、されている(同前p84)。
では関白にならない違いはどこにあったか。それは左大臣に止まり政務を行ったこと、左大臣を筆頭の上卿[しょうけい]の意で一上[いちのかみ]と呼ぶが、一上の事(一上の政務)を手放さなかったことにあったと思う。(同前p85)道長が初めて「一上」として、右大臣となったのが長徳元年(995)六月十九日である(そのとき左大臣は空席)。続いてその翌年(996)に左大臣となり、寛仁元年(1017)まで長期間「一上」としての地位を保っていた。